こんにちは 主婦ライターの洋子です。
あなたは、お中元について詳しく知っていますか?
お中元を社会人になって初めて贈る事になった場合、まず何から手を付けたらいいのか?
お中元はいつ、どうやって届ければいいのか?
送るのは、暑い間? 夏の間? お届けの作法は? マナーは? などなど
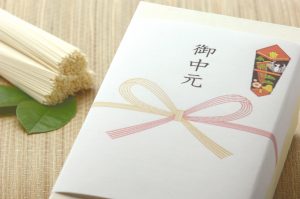
私は、社会人になっても職場の環境で、『お中元』を贈る慣習がなかった為、お中元に関しての知識がまったくありませんでした。
ですが、結婚をし、主人の会社関係にお中元を贈らなければいけなくなり、アタフタしたのを覚えています。
今は、場数を踏みましたので慣れたものですが(笑)
そんな経験をあなたにお伝えしてあなたの一助となれば嬉しいです。
お中元を送る時期はいつ? 今年は何日~何日まで
お中元…と聞いて、なんとなく「夏?」くらいの感覚はあるかと思います。
ではまず、いつ送る?時期からご説明していきます。
お中元を贈る(届ける)時期
全国的(一般的)には、お盆の中日までの約1月の間
7月15日~8月15日までの間に、相手に届くように送るとされています。

次に、地方別の時期は、下記になります。
|
地方 |
時期 |
|
北海道 中部 関西 中国 四国 (北海道、中部、最近の傾向) |
7月15日~8月15日 (7月1日~7月15日) |
|
東北 北陸甲信越 |
7月1日~7月15日 |
|
関東 |
6月下旬~7月15日 |
| 九州 |
8月初旬~8月15日 |
| 沖縄 |
7月初旬~7月15日 |
地域別では、送る時期にかなり差がある為注意が必要です。
北海道や中部地方は、関東方面から移動してくる人が多く、7月1日~7月15日頃に届く事が増えているようです。
関西地方や九州地方でも年々早まる傾向があり、7月中旬頃には届いている事が増えていて、
なんと、ここ数年では、関東方面を中心に更に早まる傾向があり、6月20日頃から送り出すことも普通になっているようです。
まだ、ボーナスも出ていない時期にどうしよう(汗)

この送る期間から遅れると『お中元』から『残暑見舞い』になります。
次は、渡し方に関してのマナーです。
お中元は、宅配業者に依頼する方がほとんどだとは思いますが、直接手渡しする事もあります。
そもそもお中元は、いつもお世話になっている方や、過去にご迷惑をおかけした人への感謝とお礼の気持ちを伝える為のものなので、直接渡せるならさらに気持ちが伝わりますし、本来はお渡しする相手のお宅へお邪魔して直接渡すのが基本的マナーです。
お中元の渡し方

お渡しする相手の住んでいる地域を確認し、渡す時期を決める
お渡しする相手の方にご都合良い日時を確認する(いきなりの訪問はNGです)
早朝・深夜・ご飯時を避ける事。また、お伺いする理由をお伝えしますが、あまりにも直接的な伝え方はNGです。「お中元を持っていきたいのですが」など。
「ご挨拶にお伺いしたいのですが」などの伝え方が良いです。
包装紙の上にのしを必ず付ける(文言は「お中元・御中元」)
必ずのしをつけましょう。文言は「お中元・御中元」

風呂敷に包んで持っていく
本来は風呂敷ですが、ここ数年で紙袋が主流となってきていますので紙袋でもOKです
お渡しする前に風呂敷を外して渡す
お渡しする前に風呂敷を外して渡す(紙袋の場合も、事前に紙袋から出して渡す)
一度取り出したお中元の品に正面を自分側に向け、机などに置く。
お渡しする前に、のしなどに誤りが無いかを再度確認をし、相手側に正面を向けて両手を添えて差し出す。
感謝の言葉を添えてお渡しします
「いつも大変お世話になっております」「心ばかりですが」など。
この時に、「つまらないものですが…」などのネガティブな言葉はNGです。
昔はよく聞きましたが、最近はあまり使いません。
「美味しいと評判なんです」などの相手のことを思いやる言葉を選びましょう。

【その他の注意点】
個人でお宅にお伺いする場合もありますが、ビジネスシーンでもお中元を渡す機会があります。
その時に注意する点は、先ほど、お中元を渡す時は風呂敷に入れて持って行くとお伝えしましたが、ビジネスシーンでは異なる事もあります。
会議室や出先で渡す事が多くなります。
その際は、持ち帰りに不便になるので、紙袋からは出さず、紙袋ごとお渡しして下さい。
渡す時は、相手の方が取っ手を持ちやすくなるようにお渡する事。
(こちらは紙袋の取っ手の下あたりを持ち、渡すようにして下さい。)
◎ こんな記事も参考になるのでは?
目上の方への注意点として、タブーな贈り物
目上の方へ贈っては失礼になるもの
- 履物
- 筆記用具や時計
- 刃物
- 現金
- お葬式の香典が連想される物(海苔やお茶)
などは、目上の方へはタブーとされていますので、贈り物選びには気を付けましょう。
目上の方に対しての、のしにも注意が必要です。
「暑中御伺い」「残暑御伺い」などの「御伺い」という言葉を使うのが本来のマナーになっています。
直接お伺い出来ない場合
本来お中元は、直接持って行き、挨拶をするのがマナーではありますが、直接お伺い出来ない事が多いです。
そして、お中元を贈る際に同梱するものに「添え状」があります。
添え状には、日頃のお礼と、送った品物、その理由などを書くようにします。
添え状を入れない、或いは忘れてしまうことがよくあるようですので、忘れずに入れるようにしましょう。
添え状が梱包出来なかった場合は、お中元が届く頃に挨拶を兼ねた手紙などを送ると良いです。
お中元の由来と現状
ここでは簡単にお中元の由来からお話ししていきます。
お中元とは、日頃の感謝の気持ちや、これからも変わらぬお付き合いをお願いする気持ち、普段はなかなか会えない方へ、お中元を通してお互いの無事を伝える物だとされています。
日本では、室町時代から始まったとされており、遠いご先祖様から代々伝わって来た伝統行事なのです。
では、室町時代に、いきなり始まったのでしょうか?
そうではありません。
歴史を遡ると、お中元の起源は中国にあるのです。
中国では「三元」があり、
上元 1月15日
中元 7月15日
下元12月15日
この「三元」のうちの一つが、中元なのです。
三元とは、神様にお供え物をし、身の汚れを清める日として定められており、その中でも、「中元」は本来、自分の犯した罪を償う日とされていました。
中元の7月15日、中国では盂蘭盆会(うらぼんえ)と言い、祖先の供養を行う日として定められていた為、中元と盂蘭盆会が一体化した行事となったのです。
その中国の盂蘭盆会が、日本に伝わり、広く一般庶民の間に広まったのです。
中国のお盆の風習として盆礼(ぼんれい)があり、この盆礼がそもそもの、お中元の起源と言われています。盆礼とは、親しい人や、感謝の気持ちを抱いている人にその気持ちを伝えることであり、生きている人にも感謝の気持ちを持とう!という日であったのです。
そして盆札を7月15日までに行うことが風習であった事と、道教の中元も7月15日に重なり、お中元と呼ばれるようになったのです。今まで、ただ何となくお中元を渡していた方は、本来の意味や由来を知るとお中元を送る時に、気持ちや品物の選び方などに変化がでそうですね。
では、次に今の現代での、お中元に何を渡しているのか、喜ばれる物は何か?と言う気になる所をお話しします。
やはりお中元は食べ物がおすすめです。

お中元おすすめの品
- 名産品
- 旬の果物
- ジュースの詰め合わせ
- アイスクリーム
- そうめん
- お酒
- おつまみや珍味

まず、お中元で「何を贈ろう?」と、しっかり考える事が大事です。
そのためには
- 家族構成は?
- 好き嫌いは?
- 子供はいた?
などをしっかり把握しておく事が重要です。
是非、普段からお世話になっている人への贈り物なので、真剣に選らんでみて下さい。
とある調査では、贈っているお中元で1番多い物はやはりビールだそうです。
年代問わずビールは人気で、2番目に上がるのが、お菓子やハム・ウィンナーの詰め合わせという調査結果もありますが、自分では買わないから…特選松坂牛!はとても喜ばれるアイテムでもありますよ!
良い動画がありましたのでご紹介します。
30秒でわかる お中元の基本おさらい
まとめ
いかがでしたでしょうか?
現代では、お中元を贈る人は半数以下だという調査結果もあります。(1000人を対象にしたアンケート)
そして、渡す相手は親せき・両親・お世話になった友人…など、渡す相手も少しずつ変化してきています。
社会人として、バリバリ働いている時は、会社関係の方にお中元を贈るという声も非常に多く、年代が上がれば上がるほど、職場関係から、プライベートの相手に贈ると言う傾向がありあす。
お中元とは先祖代々受け継がれて来ている伝統行事なので、ぜひお中元を贈り、日頃の感謝を伝えていきたいものです。
