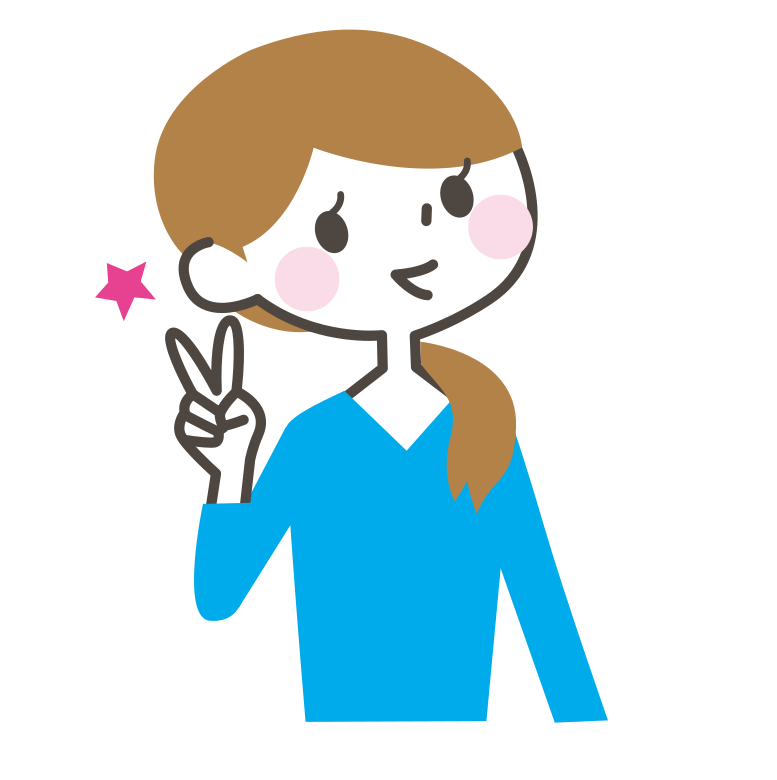もともと正義感がある性格のためか、悪いことをした犯人を追い詰める刑事ドラマは見ていて胸がスカッとします。それに、何といっても刑事ドラマはハズレが少ないのでよく見てしまうのかもしれません。

ところで、刑事ドラマを見ていると専門用語がけっこう飛び交っていますがあなたはどのくらい理解できていますか?私は自分で調べてみるまでは詳しく分からなくて、何となくのニュアンスで見ていることが多かったです。
ですが、その何となく…というのが微妙にモヤモヤさせられるものでした。
今は、自分で気になった専門用語は調べるようにしています。刑事になりきるところがあるので、主人と子どもは少しあきれていますが(笑)
専門用語の意味を知るとより刑事ドラマが楽しくなること間違いなしです。
今回は、刑事ドラマでもよく出てくる「保釈」についてご紹介していきます。
保釈とは
罪を犯した人が逮捕されるとその人は被告人と呼ばれます。逮捕された後に起訴され、裁判を経て判決が確定していきますが、その間被告人の身柄は拘束(拘留)されています。起訴されてから判決が出るまでの間、一定条件のもとで身柄の拘束を解くことができる制度を保釈といいます。
※起訴(きそ)とは、裁判所に訴えを起こすことで検察官の権限です。

保釈の条件
保釈のための条件とは、被告人が逃亡する恐れがないこと、証拠隠滅を行う恐れがないこと、保釈金を払うことなどがあります。保釈は被告人の持つ権利であり、保釈を許可するかどうかは裁判所が判断します。
保釈金について
また、保釈の際にポイントとなるのが保釈金です。保釈金が払えるか否かで、実際に保釈できるかどうかの分かれ道になります。保釈金については、別の記事に詳しく書いていますので是非ご覧ください。
◎ 保釈金についての詳しい記事はここに!
その他、保釈が認められないケースは下記のように多々あります。
保釈が認められないケース
- 保釈金が払えない
- 殺人などの重罪を犯している
- 過去にも殺人などの重罪を犯したことがある
- 常習性があり、証拠隠滅の恐れがある
- 被害者や証人に危害を与える恐れがある
- 氏名と住所が明らかでない
仮釈放との違いとは
保釈と仮釈放、この二つが混同してしまうことはありませんか?どちらも身柄の拘束を解くという点では同じなので、刑事ドラマを見ていても話がこんがらがってしまうことなどはありません。ですが、保釈と仮釈放はまったくの別物なので覚えておいてくださいね。
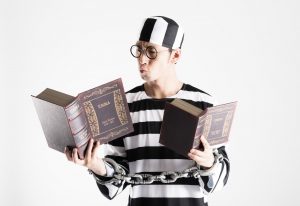
仮保釈
仮釈放とは、すでに刑を受けている受刑者を対象に使う言葉です。刑務所で服役している受刑者が刑期を終える前に出所することを仮釈放といいます。仮出所ともいい、残りの刑期を自宅などで保護観察を受けながら過ごすことになります。
つまり、保釈とは裁判で判決が出る前の被告人に対する制度、仮釈放とはすでに刑を受けている受刑者に対する制度というようにそれぞれ全く違う制度なのです。
次に保釈と仮釈放の目的についてみていきましょう。
なぜ保釈や仮釈放があるのか
どうして逮捕・起訴された被告人や刑期を終える前の受刑者の拘束を解くのでしょうか?被告人の場合は逃げてしまったり、証拠を隠滅したりするチャンスになってしまいそうです。また、受刑者についてもそもそも刑期を終える前に刑務所を出ることができるのはラッキーな話に思えるものです。
ですが、ちゃんと意味があるからこそ保釈や仮釈放という制度があるわけなんですよね!
保釈と仮釈放は、どちらも釈放された後の社会復帰を助けることを目的としている制度です。重罪の場合は別としても、刑を全うしたらいずれ社会復帰しなければなりません。
被告人の立場になって考えてみると、罪を犯したとはいえ突然身柄を拘束されるわけです。できることなら、家族や職場に話をきちんとしておきたいと考えますよね。
いきなり拘留という形で姿を消すのではなく、できる限りの準備をしておくことで後の社会復帰をスムーズにすることができます。
受刑者についても、刑を終えた途端にいきなり社会にほっぽり出されても当の本人は困惑することが多いものです。スムーズな社会復帰があってこそ、本当の更生につながっていきます。再犯を防ぐためにも社会復帰の手助けは必要不可欠であるといえるのです。
被告人にとっての保釈のメリット
- 裁判の準備に時間をかけられる
- 仕事を続けられる可能性が増える
- 服役までの時間を有効に使える
受刑者にとっての仮釈放のメリット
- スムーズに社会復帰できる
- 再犯を防ぐことにつながる
罪を犯した人が社会復帰したときに可能な限り負担を少なくできるように保釈や仮釈放の制度があります。私は、保釈と仮釈放を理解することで、罪をおかした人の人生についても考えるようになりました。罪を犯した人の人生を滅茶苦茶にするのではなく、その後どうやって更生するかが重要なのではないかと思います。
保釈されるまでの流れ
申請から保釈金を収めて開放されるまでの流れ
逮捕 → 拘留 → 起訴 → 保釈の申請 → 保釈の許可 → 保釈金納付 → 保釈

保釈の申請
保釈の申請は、起訴されてすぐ、同日に行うことができます。保釈申請をする場合は、基本的に担当の弁護士に動いてもらうものです。弁護士は保釈申請のノウハウを知り尽くしているので、保釈できるよう迅速にサポートしてもらうことができます。
身元引受人
また、保釈申請の際は身元引受人をたてる必要があります。身元引受人は被告人の監視役を担うことになりますが、もしも被告人が保釈中に問題を起こしたとしても身元引受人が責任を問われることはありません。
保釈の許可日
保釈申請から実際に保釈されるまでの期間は、土日を挟んだとしても3日以内であることが多いようです。保釈が許可されると保釈金や保釈中の制限についての言い渡しがあります。その後、保釈金を納付すると、ようやく保釈が現実のものとなります。保釈の期間は、裁判での判決が下るまでの間となりますので、約1~2ヵ月前後となるようです。
保釈申請の回数
反対に保釈申請が却下されてしまう場合もあります。その際は、再度(何度でも)、申請を行うことができますが、何か原因があって却下されていると考えるのが自然です。そのため、担当の弁護士とよく話し合いながら進めていく必要があります。
保釈中の制限とは
- 裁判所からの呼び出しには必ず出頭する
- 住所を変更する場合は裁判所の許可を得る
- 海外などへの長期の出張や旅行も事前に裁判所の許可を得る
- 被害者への連絡は必ず弁護士を通す(保釈中に被害者に会うことは禁止)
- 共犯者や証人などの事件関係者とは接触しない
保釈が認められて身柄の拘束が解かれたとはいっても罪が許されたわけではありません。
何もかも自由というわけではなく、保釈中には様々な制限がかかります。だからといって監視が付くということはありませんが、保釈中の制限や禁止されている事項は守らなくてはいけません。
仮に保釈中の制限を破った場合、保釈が取り消され、保釈金も国に没収されてしまうことがあります。保釈中の制限についてのポイントは、被告人の居場所を明確にしておくこと、事件関係者と接触しないこと、新たな問題を起こさないようにすることなどが挙げられます。(とはいえ、ドラマの中では危険を承知で関係者に接触するのはあるあるですね…笑)
まとめ
刑事ドラマを見るときの疑問を解消するために保釈についてご紹介しました。
専門用語を理解するとなんだか自分も刑事になりきってしまいますよね!
刑事ドラマ以外にもニュースなどで保釈や仮釈放といったワードは出てきますので関心がより高まるのではないでしょうか。
刑事ドラマでは犯人が逮捕されるところまでを描かれることが多いですが、その犯人に同情の気持ちを持つことも多いものです。
「罪を償ったら今度こそ幸せになってほしい」なんて想像を膨らませるなど、また新しい刑事ドラマの楽しみ方が広がると嬉しいと思います。
◎ これも一般人にはあまり縁のないことですが…